Part one 以前のこと
1.
 人生で初めてタバコの味を覚えたのは20歳の時だった。
人生で初めてタバコの味を覚えたのは20歳の時だった。
その時は丸二日間吸い続けた。カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーでのことだ。その1ヶ月前から、女友達のロニーとオレゴン州でリンゴ摘みのアルバイトをしていた。そして自分たちへのご褒美に、2人でカナダまで旅行に行くことに決めて、最初の週にコンドミニアムタイプの安っぽいホテルにステイすることになった。
今でもよく覚えているが、部屋には壁に折りたたみ収納できるベッドがあって非常に魅了された。そこに滞在した間、一番楽しかったのがベッドを折りたたんでは、そこに出来た空間を眺め。それからまたベッドを引っ張り出しては、折りたたみ、そして引っ張り出すことだった。僕は腕が疲れるまで何度も繰り返した。
ホテルから1ブロック離れた処にあった小さな店で、生まれて初めてタバコを一箱買った。その前に吸ったのは、すべてロニーからもらったタバコだった。銘柄は「ポールモール」だったと思う。味については、タバコはこんなものなのだろうと想像していた通りで、さして美味しくも不味くもない味だった。だからというわけではないが、自身の個性を打ち出す為に、「自分の銘柄というものを持たねば」と思った。
何かしら、 他の銘柄と区別できる自分らしいもの。
カールトン、ケント、アルパイン……、
まるで宗教を選択するかのよう。
「ヴァンテージ」を吸う人達は原理的に「ラーク」や 「ニューポート」を吸う人達と相違ないのか?
僕がその時認識できなかったのは、「タバコは改宗が可能」で、それが許される事だった。「ケント派」は、ほんの少しの努力で「ヴァンテージ派に」改めることが出来る。しかし、「メンソール派」から「レギュラー派」への改宗は難しい。「レギュラーサイズ派」から「ウルトラロング派」への改宗 も同じく苦労を伴う。
全ての規範には例外が伴うが、ことタバコに関しては、一般的に次のような規則性を見つけることが出来た。
「クール」と」「ニューポート」は、黒人か白人低所得者の銘柄。
「キャメル」しなければならないことをぐずぐずと引き伸ばす因循家。下手な詩を書く、あるいは下手な詩を書くことを先延ばしにするような人達。
「メリット」はセックス中毒症。
「セーラム」はアルコール中毒。
「モア」は自身をとてつもない存在と思っているが、実際傍から見ると至って普通である。
「マルボロメンソール」を吸っている人には決してお金を貸してはならないが、「マルボロのレギュラー」だと、通常は確実に返金してもらえると見て良い。
以上のような 分類をしていると避けることが出来ない結果だが、下位区分のマイルド、ライトやウルトラライトは、この規則性を更に混乱させるだけではなく、自身の銘柄を決定し固定させるのをほぼ不可能にしてしまった。でもこういったことは全て、後に喫煙への警告ラベルとアメリカンスピリットについて一緒に書くことにする。
あの日にバンクーバーで買ったのは、「バイスロイ」だった。この銘柄はガソリンスタンドのサービスマンが シャツのポケットによくいれていた。だから、このタバコを吸えば男らしく見える事を疑わなかった。少なくともベレー帽にギャバン地で踵にボタンのついたズ ボンを履いているぐらい男らしく見えると思った。ロニーの白いシルクのスカーフに差し挟んで、買えるだけたくさん「バイスロイ」を買った。僕達の滞在していたホテル界隈では必要だったからだ。
おかしなことだが、 僕はそれまで常にカナダは平和で安全な国だと聞いていた。でもそれは、カナダでも違った地方の事。たぶんカナダ中央部、それとも東部の岩山に囲まれた島々等のことだったのだろう。僕の滞在した場所では、酔っ払いに次々と出くわした。今すれ違った奴はさほど酷くはなかったが、前からこっちに向かってくる奴はふらふらしながら手をバタバタと激しく揺らしている。一瞬、生命の危機を感じた。
僕が店を出た後に近づいてきた男は、長い黒髪を編んで後ろに垂らしていた。それは上品でちょっと身体の調子が悪そうなフルートを吹いているような三つ編男ではなかった。その三つ編は「牛追い鞭」に近いものを連想させた。そう、囚人の三つ編だ。一か月前の僕がこの男に遭遇していたら、きっと怖気づいていただろう。でも僕はタバコを口に咥えていた。人が処刑される寸前に最後のタバコを吸うように、きっと奴は僕を脅し金を奪うだろう。そして三つ編で僕を鞭打ち、僕に火を放つだろう……。でも、そうはならなかった。「一本くれよ」 と言って、僕の持っていたタバコの箱を指差した。僕はバイスロイを彼に渡した。礼を言われた時に僕も笑って彼に感謝した。
それは、後で思ったことなのだが。僕が花束を持って歩いていて、その男がデイジーを1本欲しがったようなものだった。彼は花を愛し、僕も花を愛している。そして僕達の相互理解が僕達の様々な相違を超越し、何かしら僕達を結び合わせるのは非常に美しいことではなかっただろうか? 次のようにも考えてみた。もし僕らが逆の立場だったら、彼は僕に喜んでタバコを一本くれただろう。でも僕のこの理論を実際に立証することは敢えてしなかった。僕はボーイスカウトに2年しか在籍しなかったが、ボーイスカウトのモットー 「備えよ常に」は永遠に従う金言だった。この金言は「人にクソみたいな事を頼むことに備えよ」というだけでなく、「特に己の悪徳に関しては、先を見越して備えよ」という意味だった。
2.
 小学校4年生の時、クラスの遠足でダーラム近郊にあるアメリカンタバコ社の工場に行った。タバコの生産を見学した後、両親へのおみやげにとタバコを数箱もらった。この事を人に話すと、みんな僕が何歳なのか訊いてくる。たぶん、僕が世界で最初に創立された小学校に通っていたと思っているのだろう。洞窟の壁に文字を書き、昼食はこん棒をもって猟に出るような学校。高校時代に学校に喫煙ラウンジが在ったと話した時には、また自分の年齢をいわなければならなかった。喫煙ラウンジはもちろん屋外にあったが、今の時代はそういったものは皆無であろう。たとえ、監獄内の学校であっても。
小学校4年生の時、クラスの遠足でダーラム近郊にあるアメリカンタバコ社の工場に行った。タバコの生産を見学した後、両親へのおみやげにとタバコを数箱もらった。この事を人に話すと、みんな僕が何歳なのか訊いてくる。たぶん、僕が世界で最初に創立された小学校に通っていたと思っているのだろう。洞窟の壁に文字を書き、昼食はこん棒をもって猟に出るような学校。高校時代に学校に喫煙ラウンジが在ったと話した時には、また自分の年齢をいわなければならなかった。喫煙ラウンジはもちろん屋外にあったが、今の時代はそういったものは皆無であろう。たとえ、監獄内の学校であっても。
映画館や食品雑貨店に昔は灰皿が置いてあったのを覚えている。だからといって喫煙したいと当時は思わなかった。寧ろその逆だった。一度母親のウィンストンの箱に刺繍針をブスブスと刺して、ブードゥー人形の呪いをかけるような悪戯をした。母親は、それを見つけるやいなや、20秒間僕を叩き続けた。その時母親は息が切れ、浅い呼吸に喘ぎながら言った。
「こんな……こと……おも……しろく……、ないわよ……」
それから何年か経って、朝食の後にテーブルに座っていると、母親が僕に一口タバコを吸わせてみた。すると僕は一気に台所に走って行き、オレンジジュースを1パック一気に飲み干した。猛烈な勢いで飲んだので、ジュースの半分は僕の顎を伝ってシャツにかかってしまった。母親はなんでこの様なものを、母だけでなく、他の人達も、こんな根本的に不快なものを常用するのだろう? 姉のリサが喫煙を始めた時、僕はリサに火のついたタ バコを持ったまま僕の部屋に入ってくるのを禁じた。部屋の敷居の外から話すこと、煙を吐くときは顔を向こうにそむけて吐き出すようにしてもらった。もう1人の姉のグレッチェンが喫煙を始めた時も同じようにしてもらった。
僕はタバコの煙ではなく、その臭いが嫌いだった。後年になると、臭いは気にならなくなったが、当時はその臭いを気分が沈み込むようなものと感じていた。怠慢や無関心、放置の匂いと思っていた。家の中のほかの場所ではそれと分かるものではなかったが、家の中のほかの場所は無関心に放置されていた。一方僕の部屋は綺麗で整然としていた。僕の 部屋の保ち方では、真新しいアルバムジャケットのビニールカバーを取ったときのような匂いがするはずだった。少なくとも、僕の部屋は希望の香りがしていた。
3.
 14歳の時にクラスメートに連れ添ってラレイ公園に行った。そのクラスメートの友達の何人かに会って、月明かりの下でジョイント(マリファナ)を吸った。ハイになった記憶はないが、ハイになった振りをした記憶はある。僕のとった行動は、以前テレビや映画で観たフラフラになったヒッピーを手本にした。基本的に何に対しても本来可笑しいかどうか関係なく、とにもかくにも沢山笑っただけだ。家に着いた時、姉達を起こし自分の指の匂いを嗅がせた。「ほら、匂うだろ?」、と僕は言った。「マリファナだよ。【ハッパ】 ともいうけどね。」
14歳の時にクラスメートに連れ添ってラレイ公園に行った。そのクラスメートの友達の何人かに会って、月明かりの下でジョイント(マリファナ)を吸った。ハイになった記憶はないが、ハイになった振りをした記憶はある。僕のとった行動は、以前テレビや映画で観たフラフラになったヒッピーを手本にした。基本的に何に対しても本来可笑しいかどうか関係なく、とにもかくにも沢山笑っただけだ。家に着いた時、姉達を起こし自分の指の匂いを嗅がせた。「ほら、匂うだろ?」、と僕は言った。「マリファナだよ。【ハッパ】 ともいうけどね。」
家族の中で自分が一番にジョイントを吸ったことを誇りに思った。でも、一度このタイトルを獲得してからは、猛烈なドラッグ反対論者となり、大学の一年生になるまでその状態が続いた。1年生最初の1学期、学生寮の友達に対して、「ポット(マリファナ)は負け犬がやるもんだ。脳みそがやられちまってるから、こんなクソ州立大学にしか入学できないんだよ」と嘲っていた。
その友人達にとって、どれだけ満足のいくものだったのか後になって思い返してみた。本当に聖書の中にある話みたいに、友人たちは僕の完全な路線変更を目の当たりにしたのだ。尊敬を集める母親が街のアバズレになり、禁酒法支持者が酔っ払い、僕はマリファナ常用者となった。それも物凄い速さで。まるで映画に出てくる話みたいに。
寮の階下の気さくな友達:ほら、やってみなよ。ちょっと一口吸うだけで、何の害もないからさ。
僕:ああ、わかってるよ。俺は勉強しなきゃならないんだ。
寮の階下の気さくな友達のハンサムなルームメイト: ショットガンさせて。
僕:ショットガン? 何それ?
ハンサムなルームメイト(再び): 君が横たわって、僕が君の口にポットの煙を吹き込むんだ。
僕:どこで横になったらいい?
あの夜自分の部屋に帰って、シルクのスカーフで電気スタンドにカバーをした。机、ベッド、アートクラスの課題の大きくて不恰好な陶器。どれも新しいものではなかっ たが、全てが違って見えた。何か新鮮で興味をそそられるもの。盲目の人がモノを見られるようになったとしたら、きっとその時の僕の反応と同じものだろう。部屋の中をゆっくりと横切りながら、目の前にあるもの全てが不思議でならなかった。畳んだシャツ、 積み上げられた本、アルミホイルに包まれたコーンブレッド一切れ。驚嘆する凄さ。部屋のツアーは鏡の前で終わりを迎えた。ターバンを頭に巻いた自分の姿を見て、「やあ、こんちは。あれ、君そこにいたの」、と自分に感心していた。
大学の同級生にショットガンをお見舞いされてからの23年間、僕の生活はハイになる事を中心に回っているようだった。実際、僕がタバコを吸い始めたのもマリファナがきっかけだった。ロニーと僕はハイウェイの道端でカナダに向かってヒッチハイクをしようとしていた。僕はマリファナが手持ちにないことをぶつくさ愚痴っていた。全てのものが同じに見える、そのことで僕の神経は苛立っていた。そこで、ロニーにタバコを吸うと気分が変わるものか訊いてみた。
ロニーはタバコに一本火をつけて、暫く考えていた。
「そうねえ、ちょっとめまいがするかなあ……」と彼女は言った。
「それって、吐き気がするってこと?」
「ちょっとね」と彼女は言った。それで、僕は十分いけると思って始めた。
4.
マリファナと同様にタバコを常用し始めたのは異常に早かった。まるで僕の人生に演劇でいう小道具係が登場したような。突如として、タバコの箱という箱を開けては、マッチを すった。灰皿を一杯にしては、また空っぽに。僕の両手は、料理人、あるいは編み物をしている人のように、片方だけで用事をするようになった。
「やれやれ、それはお前の身体に自分で毒を盛っているようなものだよ」と、父親は僕に言った。
一方母親のほうは、むしろ明るく捉えていた。
「これで、クリスマスにお前の靴下に何を入れるか迷わないで済むわ!」
母はイースターのお祝いにもタバコを丸々カートン箱ごとくれた。現在では母親が息子のタバコに火をつける姿なんて下品なものだと皆は考えているのかもしれない。でも当時は喫煙自体が何かしらの意味を持つ行為ではなかった。
僕が喫煙を始めた頃は、職場で喫煙することが出来た。たとえ病院勤めであってもそれは可能で、両足のない子供が下半身を歩行器に括り付けられている隣でもタバコを吸うことが出来た。TV番組で登場人物が喫煙しても、必ずしもその人が人間的に弱いとか悪い人間であるということではなかった。喫煙は人がストライプのネクタイをしていたり、髪形を左側で七三に分けていたりするようなものだった。それはその人の細かい特徴で、わざわざ指摘する必要はなかった。
僕自身スモーカーに特別に注意を払うことは80年代半ばまではなかった。その頃からスモーカー達は防備線を張られだした。今は待合室やレストランでも喫煙エリアが分けられている。よく僕は辺りを見廻して、今は「僕のチーム」と考えるようになった人々を評価するようになった。「僕のチーム」の人達は、最初のうちは十分ノーマルに見える。普通の人々。でも彼らは手にタバコを持っていた。
その後、熱烈なキャンペーンが開始された。室内で「僕のチーム」側区域で10人がタバコを吸っている場合、少なくとも同じ室内のノンスモーカー1人が淀んだ空気の中で受動喫煙してしまうということだった。
「まだそれがクールだと思っているの?」とあちら側の人々が言って来た。しかし、この「クール」とか「格好がいい」という概念は、僕達の中の多くにとって、喫煙とは全く関係のないものだった。
スモーカー1人1人が洗脳されていて、タバコの生産者側の販売促進や印刷広告に呑み込まれてしまっていると多くの人々が信じていた。この論争はスモーカーを責めるのに便利である。でも、これは喫煙が時に素晴らしいものであるという事実を無視している。僕のようなスモーカー達はビクビクと引き攣った表情をしながら小さいながらも悲痛な叫び声を上げている。
タバコは天の賜物だ。それだけではない。タバコは美味い。特に朝起きたときの最初の一本。それからその直後に続けて吸う7、8本は……。
午後遅くなる1箱全部吸い終わってしまい、その頃には肺が重くなってくる。80年代はこれが顕著な状態だった。その頃僕は有害な薬物を常用していた。実際は人工呼吸装置でもつけておいたほうが良かった程だが、タバコを吸うのに邪魔になるので止めておいた。
僕は一度この事について、犯罪病理学の先生に相談しにいった。僕は医療検査課の検屍室に連れていかれた。先生は僕に検屍解剖して取り出した肺を僕に持たせた。これは肥満体の薄い肌色をした黒人男性の肺だった。ヘビースモーカーなのは明らかで、遺体は僕から3フィートも離れていないところに台の上に横たわっていた。胸骨が開かれていて、その中から掘り出されたサワークリームみたいな脂肪を見て、僕はベイクドポテトを連想した。
「どうでしょう」と先生は言った。
「これをご覧になって何か仰ることは?」
先生はまさにこの瞬間を待っていたのは明らかで、僕の今後の人生を変える瞬間になる筈だった。でも実際はそうはならなかった。
今これを読んでいる君が、仮に医者だとしてみよう。そして、病理を持った肺を手渡されたとする。すると、君はそれを綿密に検査して、結果的にこの肺は知識や意識に大きな変革をもたらすことになるだろう。ところが、この仮定を逆に考えて、貴方が医者でない場合、きっと僕がとった行動と全く同じ反応を示すと思う。僕はそこに立ち尽くしたまま考えていた。
「うわっ、この肺クソ重てえ」
5.
 ニューヨークでレストランでの喫煙が禁止された時、僕は外食するのを止めた。職場での喫煙が禁止されたら、僕は仕事を止めた。次にタバコ箱の値段が7ドルに値上がりした時は、僕は荷物をまとめてフランスに引っ越した。
ニューヨークでレストランでの喫煙が禁止された時、僕は外食するのを止めた。職場での喫煙が禁止されたら、僕は仕事を止めた。次にタバコ箱の値段が7ドルに値上がりした時は、僕は荷物をまとめてフランスに引っ越した。
フランスで僕の吸っていた銘柄を見つけるのは大変だったが、そんな事は構わなかった。少なくとも年に2回は米国に帰り、パリに戻る際、空港の免税店で1箱20ドルのカートンを15パック買い飛行機に乗ってしまえばよかった。
おまけにアメリカからパリに訪ねてくる友人からおみやげにタバコをもらった。友人達はいわばクスリの売人の役割をしていたわけだ。母親が亡くなった後でさえ、クリスマスとイースターに家族からタバコをプレゼントに貰い続けた。火事や盗難に常に備え、ピーク時には、30から40 箱のカートンをストックとして家の中で3箇所に振り分けて保管していた。それらを「我が在庫」と僕は呼んでいた。こんな風な事をよく言っていたものだ。
「俺がノイローゼになるとしたら、唯一の原因は『我が在庫』さ」
ここで告白するが、僕はクールマイルド派だ。
これはいってみると、ワイン愛飲家が様々なワインを飲み試す過程で、最も好んで飲むワインが実はランサーワインだったという話みたいなものだ。でもそれでいいと思っている。メンソールの味を僕に教えたのは、妹のグレッチェンだ。妹は高校時代にカフェテリアでバイトをしていて、そこのシェフのデューベリーから 「クール」を勧められて吸うようになった。僕はそのデューベリー本人に会ったことはなかったが、タバコを吸い始めた最初の2、3年は、息が切れる度にデューベリーの事を考えた。
もしデューベリーが「タレイトン」を吸っていたとしたら、僕の人生はどんなものになっていた事だろう。「クール」にはファイバーグラスが使用されていると言われていた。もちろんこれは単なる噂で、それを広めたのは「セーラム」や「ニューポート」派だと思う。メンソールはレギュラータイプより身体に悪いと僕も耳にした事がある。しかし、これも事実かどうかは疑わしい。
母親が放射線治療を始めた頃、僕にクールマイルドのカートンを一箱送ってきた。「セール品よ」としわがれ声で母が言った。死ぬのであれ、生きるのであれ、母は僕がキングフィルタータイプを吸っている事を知っておくべきだと当時は思った。しかし僕はその箱を見てつぶやいた。
――いいや、これはタダだもんな。
吸わない人にとって、マイルドやライトタイプはレギュラータイプに小さな孔が空いているようなものと思っていると思う。クールに関していえば、裸足のロバに蹴飛ばされるか、靴下を履いたロバに蹴飛ばされるかの違いだ。慣れるのに多少時間がかかるが、母親が火葬される頃には、僕はすっかりマイルド派に改宗していた。
6.
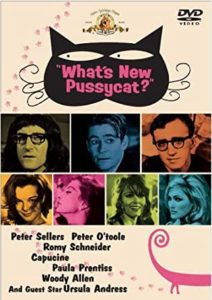 過去 何年かの間に、僕のエッセイがたくさん教科書に使われるようになった。高校生やそれより下の年代向けの教科書の場合、編集者は文章中の汚い表現や不道徳な言葉やフレーズを書き換えたり、削除したりしてもよいかと訊ねてきた。これは僕も理解は出来た。唯一理解できなかったのは、少なくとも同じような理由で、タバコを削除しても良いかと要請があったことだ。
過去 何年かの間に、僕のエッセイがたくさん教科書に使われるようになった。高校生やそれより下の年代向けの教科書の場合、編集者は文章中の汚い表現や不道徳な言葉やフレーズを書き換えたり、削除したりしてもよいかと訊ねてきた。これは僕も理解は出来た。唯一理解できなかったのは、少なくとも同じような理由で、タバコを削除しても良いかと要請があったことだ。
それも 「-」で空白に置き換える方法(一般的に罵り語などを表記する場合に用いる)をとるというものだった。最近は写真においても、空白にする方法をとるようだが、効果としては、読者や見る人が面食らうだろうし、混乱するだけのものだと思う。
ここにマレーネ・デートリッヒが一休みしている写真がある。意味もなく人さし指と中指を開いて立てている。その眼差しは燃えている宙の何もない先端を見つめている。この教科書は高校生向けの「ホライゾン(地平、思考、知識 の視野 の意味)」だったか、「視点」という名前だったような気がする。
編集者が削除したがった一行は、特に喫煙を賛美するようなものでもなかった。実際はその逆で、そこに書かれているタバコは、僕の母親が吸っているもので、それを僕は文章中で刺激物として言及していた。僕はタバコのことを、僕自身が侵害されたような気分になるもので、頭痛がしてくるものと表現していた。僕がこの文章中の単語を置き換えると仮定して、この癪に障る「ウィンストン」の部分を「筒型花火」にしたとしよう。物語は真実を語らなければならない。僕の母親は決して花火を口に咥えて座わることはない。
僕が主張したかった点は、 世の中には喫煙する人がいるという事だ。喫煙はそういう人達を形作るものの一部分であり、人がそれをどうしても嫌わなければならないものでもない。他人の人格を変えてしまおうなんて、少し荒っぽいやり方だし、特に自分の母親となると、タバコを手にしていない姿を想像するのは困難だ。
「母のタバコは おちょくりネタのおもちゃみたいなもので、それが母の持ち味だったので」と僕は言っておいた。教科書から喫煙家の母親を排除するなんておかしなことだと 思ったが、しかし、その後数年の間に喫煙は映画の中でも禁止されるようになった。
女性が生まれたばかりの子供を高層ビールの屋上から放り投げることは可能で、それから死体を持ってきて踏みつけ、保育園の窓に向かって銃を撃ち込み続けることも可能だ。しかし、こういった一連の殺戮行為をタバコに火をつけて祝うことは有害なメッセージを送るものだと考えられている。結局若者が視聴することで、間違った考えを持たせないようにする為であろう。
我々スモーカーは永年、受動喫煙について警告され続けてきた。でもこれが本当に主張されている通りだとしたら、僕は1歳の誕生日まで生存していなかっただろう。僕の兄弟姉妹も死んでいたと思う。大体、僕も含めて最初から生まれてくることもなかっただろう。僕の母親は母のそのまた両親が吸うタバコの煙を吸いながら大きくなったからだ。
僕の父方の祖父母は喫煙者ではなかったが、ニューススタンドとタバコ屋を生業としていた。祖父母は他人様が煙草を吸うことで生計をたてていたわけだ。僕の父親は大学に通うようになってからタバコを吸い始めた。でも父は、僕の姉や僕が小さい時に喫煙を止めてしまっていた。「タバコなんて、薄汚い習慣だ」と一日に50回は言っていたが、これは何の効果もなかった。
煙草のパッケージに警告文が印刷され始める前にも、誰もが喫煙が身体に良くないことを分かっていた。母の妹のジョイス叔母さんは外科医と結婚した。僕が叔母の家に泊まりにいく度に、明け方に必ず叔父さんの空咳で目を覚ました。それは不愉快で痛々しい咳声で、今にも死にそうな感じだった。その後、朝食のテーブルで叔父さんがタバコを咥えている姿を見て僕は思ったものだ。
そうさ。おじさんは医者だもんな。
ディック叔父さんは 肺ガンで亡くなった。そのあと数年後には今度は僕の母親が叔父と全く同じような空咳をするようになった。母は女性だから、もっとソフトで繊細な咳をすると思うかも知れないが、ノーとハッキリ否定しておこう。ベッドに横になりながら、当時僕は気恥ずかしい気持ちがいっぱいになりながらよく思ったものだ。
母さんの咳、男みたいだ。
僕のこの恥ずかしさや困惑が心配へと変化した頃には、母親にタバコについて警告を垂れる意味を僕自身が失くしていた。僕もスモーカーとなっていたからだ。僕に何が言えただろう。本当に。最終的に母はウィンストンを止めて、ライトタイプを好むようになり、それからウルトラライトに変えた。「なんか、ストローでも吸ってるみたい」と、文句を言っては、「ちょっと、お前の吸ってるのちょうだいよ、ねえ?」と言っていた。
僕がシカゴに住んでいた時に、母が訪ねてきた。最初は大学卒業の時だ。その2、3年後にまた訪ねてきた。母は60歳になったばかりで、一緒に歩く時にはペースをゆっく りにしてやらなければならなかったのを覚えている。電車に乗るのにホームまで上がる時は、階段を5段ずつ上がっては、休憩しなければならなかった。その間母は、ゼイゼイと喘ぎ、つばを吐き出しては、胸を拳で叩いていた。
「ちょっとお」と僕は呼びかけ、「早くしてくれよー」と思っていた。
僕がニューヨークに移り住んだ頃、母さんがいろいろな事をこなしている姿を想像しようとしてみた。銀行まで車を運転し洗濯して、キッチンでポータブルTVを見ている母親。 その姿の口元には舌と歯は別として何もない。母はその頃、委託販売の店にパートにでていた。その店はイージーエレガンスと呼ばれていた。母は僕にすぐに電話をしてきて、その店は何でも取り扱っているわけではなく、
「高級品じゃなきゃ、ダメなのよ」と言っていた。
店のオーナーは喫煙を認めなかった。だから母は数時間おきに店の裏口のドアから外に出なければならなかった。駐車場の熱い砂利の上に立ちながら、母は喫煙というものが、実は洗練されていないものだと考えるようになったのだと思う。しかし2週間の禁煙のあとに僕に電話してきた時の母の声には達成感に満ちたものがあった。
「朝が一番辛いわね」と母は言った。
「それから、そのあともね。もちろんよ、飲んでる時なんてねぇ……」
何が原因で母がまた 喫煙を再開したのかは知らない。ストレス、長年の習慣、それとももう止めるには歳が行き過ぎていたということだろうか。僕も母に賛成したと思うが、今はその考えには反対だ。61歳なんて、何でもない年齢だ。禁煙を決心して試みるのに他にも理由はあると思う。でも、どれも数日しかもたない。姉のリサから母親が18時間も禁煙していたと報せがあった。それから母が電話してきた時に、ライターで火をつける音がした。それから耳障りな息を吸い込む音がして、母が言った。
「何か用、子猫チャン?」
7.
 最初のタバコから最後の一本を吸うまでの間、いつしか僕は仕事で出張にするようになった。 僕の仕事は朗読をすることだった。僕には沢山の自分の区域があって、最初のうちは古くから知っている場所に滞在することに満足していた。
最初のタバコから最後の一本を吸うまでの間、いつしか僕は仕事で出張にするようになった。 僕の仕事は朗読をすることだった。僕には沢山の自分の区域があって、最初のうちは古くから知っている場所に滞在することに満足していた。
例えば、空港近くのホリデイ・インやラマダホテルなど。ベッドカバーはつるつるで、シミが目立たないダークカラーの模様入り。廊下のカーペットには所々に押しつぶされた食品トレーが置いてあり、ルームサービスと思われるハンバーガーやフレンチトーストの食べこぼしが付いている。おい、どこまでダサいんだ? 滞在施設に目が肥えてくるのにそう時間はかからなかった。自費で三流ホテルに泊まるのは致し方ないとしても、「よそ様が払う場合は一流ホテルにステイする必要がある」、というのが本音だ。
今日の僕の様な、「いけ好かないスノッブ」を生んだ場所。それは高級と一般に呼ばれるホテルや「馬鹿馬鹿しい程に高級」なホテルであった。 シーツには製造されたばかりの刷りたてホヤホヤのタグが貼り付けてあり、コーヒーテーブルには、フルーツとワインが一本など、常にウェルカムギフトが置いてあったりする。ギフトの横にはホテルマネージャーからの手書きのメッセージカードがあり、僕をゲストに迎えられてどんなに喜ばしいかが書いてある。
「何かご必要な際、どのような事でも次の番号にお電話をくださいませ。」
早速電話して、子馬を一頭連れてくるように言おうかと誘惑にかられた。
「早くしてくれよ、おっさん。俺の気分はすぐに変わりやすいんだよ!!」
もちろん、そんな事はしなかった。それは僕がシャイ過ぎたからだと思われ……。それとも、絶対にそんな事をしたら、相手を困惑させてしまうとハッキリし過ぎていたからだと思われ……。
この様な僕のスノッブな態度が、かれこれ10年以上も続いているが、一方で僕は人の手を煩わせることにまだ躊躇してしまう。一度誰かがケーキを僕の部屋に贈ってきた。フロントに電話をしてフォークとナイフを頼む代わりに、僕はクレジットカードでケーキを切って、一切れずつ指を使って食べた。
僕が出張に行き始めた時、まだ喫煙は可能だった。80年代程ではないけれど、ほとんどの場所で喫煙は許容されていた。一度タバコを吸う為にターミナル駅の反対側まで歩かなければならない事に苦情を言った記憶がある。 振り返ってみると、そんな事は、なんでもない出来事だ。90年代になると、生活が目まぐるしく困難になってきた。 空港のバーやレストランが「クリーンエアーゾーン」になった。そして、数少ない喫煙可能な空港には、ゾッとする水槽の様な「喫煙ルーム」なるものが設置され始めた。
ソルトレイクシティ空港の喫煙ルームは、比較的良い状態だったが、セントルイスやアトランタの喫煙所は、小さなガラス張りの薄汚れた小部屋だった。 灰皿は常に溢れかえり、床はゴミだらけ、通風管はむき出しのままキャラメル色になった天井からぶら下がっていた。
常にそこに居た僕の古き良き友。彼の喉には孔が開いている。そして彼の妻。スーツケースを片手に、もう片方の手には酸素ボンベを持っている。その隣にはアブグレイブ収容所から来た軍人。刑事に手錠で繋がれた囚人2人。それと農民一家。まるで禁煙用CMだ。 その前を通る人々は立ち止まっては、こちらを指差した。特に子連れの人たちは、
「ほら、あのチューブを鼻に突っ込んでいる女の人を見てごらん。あんな風になりたいかい?」と言っている。
この様な喫煙ルームの中で、僕は車椅子の2歳児の母親の隣に座っていた。普通ならこういう親子に対してペンライトを振って応援するような人々も出てくるだろう。僕はこの母親がそういった反応を完全に無視している態度に感心していた。母親はセーラムを4分の3箱ぐらいバクバク続けざまに吸った後、灰皿に向かっ て吸殻を投げつけ叫んだ。
「あー、うまかった!」
喫煙ルームが汚ければ汚いほど、僕はそこに背を向けて逃げ出すことが出来なかった。僕の別の選択肢は屋外に出ることだった。9.11事件後、屋外に出ることが日増しに複雑になり、時間がかるようになった。大きな空港になると、メインゲートに着くまで30分はかかる。ゲートから10メートル歩き、20メートル、30メートルと歩いて、やっとドアがあった。外ではスクールバス並みに大きな車が行きかう。運転手は(大体独りで運転席に座っているのだが)あの特異な目つきでこちらを見ている。
「おい、このプカプカ野郎、空気を汚してくれて、ありがとよ」
21世紀になると禁煙区域がさらに増えていった。この新区域は全マリオットホテルをも含むようになった。
マリオット自体は別に構いはしないけれど……。 糞、マリオットの馬鹿野郎!!
マリオットグループにはリッツカールトン社も入っていた。そしてリッツカールトン社がその方針に従いだした時、僕はスーツケースの上に座って泣いた。商業施設だけでなく、町全体が禁煙区域になっていった。そういった地域は地図上では重要な場所ではないが、それでもメッセージを投げかけたいのだと思う。 その町のバーやレストランでタバコを味わうことが出来ると判ったら、その町のホテルでも吸う事が出来ると考えるだろう。パルーカヴィルのハイアットで旅行者がテーブルに座ってもタバコを吸わないという事で、きっとパルーカヴィルの人々は夜ぐっすりと眠る事が出来るのだろう。
しかし、このような一連の出来事は、いよいよ来る「終わりの始まり」を予言するものに過ぎなかった。何故 皮肉なことに悪は善より広がりやすいものなのか、僕にはわからない。
しかし、世の中とはそういうものだ。 そして、とうとう禁煙法が包括的に施行された。
そして僕は街の境界線の外に追いやられてしまった。パンケーキの店やマフラー屋の建物周辺のいたるところにある宣伝広告。人々は気付かないだろうが、どんな場所にでもホテルがあるのは確かだ。 さて、そのホテルだが、プールがないのにロビーは消毒薬のような匂いがする。それと仄かに漂うフライドポテトの匂い。 そうか、フライドポテトをルームサービスで頼めるようだ。ここに泊まった人はケチャップも一緒に頼んだようだ。ふーーん?? 電話についてるケチャップをちゃんと拭いておこう。あれ、ドアノブにもついてるな……。壁のヒーターやエアコンにもついてる……。あれ、マスタードかよ!これも拭いてと。
このホテルの部屋より更に酷いのが喫煙ルームだった。少しは新鮮な空気が入ってきていたのでそんなに悪くはなかったが、窓はハンダ付けされていて完全に閉め切られていた。 もし窓が開いていたとしても、4分の1インチぐらいしか開いておらず、このような場合は急いで吸って逃げる必要があった。どこにも逃れられないしつこい煙は、消臭スプレーで消されていた。効果はいろいろだ。目一杯になった灰皿やグラスの底に残ったレモネードに浸かった吸殻を思い出させる香りがした。 最悪、ミイラを燃やしているような匂いがすることもあった。
自身を落ちぶれさせるようなホテルには必ずエレベーターにポスターが貼ってあった。
「当ホテルのディープディッシュピザは、パンタスティック!!」
「フィンガーステーキやアペティーザーは、『パースペクティブズ(視点)』と「ホライゾンズ(視野)」で10時までオーダー可能」
請求書の端には、必ず「当ホテルは観光にも最適です!!」と書いてある。部屋には更に食べ物の写真が満載である。ほとんどが電話や時計つきのラジオに立てかけてある立体型のメニュー紹介で、ベーコンが美味しそうに撮られていることはまずないと言っておこう。更に、ベッドサイドテーブルにまでこの様な写真が置いてある時がある。ナチョスの写真も同様。ただナチョスは元来フォトジェニックでないだけかもしれないけど。
僕の部屋が1階にある場合、窓の外に見えるのは車輪が18個もついているようなトラックが停まっている風景。階上に泊まったら、時折パンケーキ屋の駐車場が見えることがある。その向こうにはインターステート高速道路が見える。その風景を描写する一番良い言葉は「歩行者の敵」だろう。散歩をするなんて絶対無理。だから僕は大概部屋の中で、銃で自分の頭を撃ちぬくことばかり考えてしまう。
いいホテルなら、お風呂を楽しみに出来るのだが、このホテルのバスタブは浅くてファイバーガラス製だ。排水栓がない時、これは普段から大体ないのだが、ビ ニール袋を丸めて栓の代わりに排水口に詰める。お湯は3分経つと水に変わる。だから僕はただそのまま横たわっているしかない。僕とビスケットぐらいの大きさの石鹸。その石鹸もカーペットみたいな匂いがする。
僕は自身に問いかけてみた。タバコを吸いたいが為にこの場所に泊まっているのだろう?それでは、そうするしかないではないか。
リッツカールトンなんか知ったことか!! 清教徒みたいなタウンカウンシル(町議会)なんかくたばりやがれ!!
40歳近くまで、上等なシーツで寝たことはなかったけど、またこの歳でこんな有様とは……。 僕はこの状態で2006年の秋までなんとか耐えた。でもこの決心も決して強いものではなかった。 僕は部屋のリモコンにどう見ても精液としか思えない塊を見つけた時、考えてもみなかった事を考えるようになっていた。
8.
 禁煙の第一歩が決心だとしたら、結果的に生じる空席を埋めておく必要があった。僕は喫煙ワールドに穴を開けることが嫌だった。だから僕は自分の代わりになる人間を探した。喫煙ワールドの人々は僕が居なくなる事を悲しんでくれた。僕の抜けた空席に関係なく、この女の子は、高校を卒業したら、きっと喫煙を始めていただろう。特にコミュニティカレッジに入学した場合、タバコの常用は絶対に避けることはできないものだ。
禁煙の第一歩が決心だとしたら、結果的に生じる空席を埋めておく必要があった。僕は喫煙ワールドに穴を開けることが嫌だった。だから僕は自分の代わりになる人間を探した。喫煙ワールドの人々は僕が居なくなる事を悲しんでくれた。僕の抜けた空席に関係なく、この女の子は、高校を卒業したら、きっと喫煙を始めていただろう。特にコミュニティカレッジに入学した場合、タバコの常用は絶対に避けることはできないものだ。
こうして自分の「やらなければならない事」リストから「代理交代」の項目をチェックし終えたら、次に3つ目のステップに進んだ。専門家によると、禁煙の一番の方法は環境を変えることだった。
日々やらなくてはならない仕事を変えてみる。非常に慎重かつ責任の重い仕事をしている人等は、ソファーの位置を変えてみたり、レンタカーを職場まで運転したりするだけでも十分だそうだ。そんなに真剣でもなく、責任の重さも伴わない仕事であれば、解決法は2,3ヶ月(日常生活から)逃避することである。新しい視野、新しい予定、そして人生の新たな時間。 世界地図を広げて逃避する場所を探した。ヒューは過去に自分の足で踏んだことのある土地をピックアップした。ヒューの一番のお勧めはベイルートだった。そこで幼稚園に通っていたらしい。ヒューの家族は60年代半ばにベイルートからコンゴ共和国に引越しした。その後はエチオピア、その次はソマリアに移り住んだ。ヒューによると、これらの土地は全て素晴らしかったらしい。
「アフリカと中近東は、俺が生きることを止めたいと決心する時までとっておこう」と僕は言った。
最終的に僕達は東京に行くことで落ち着いた。その前年の夏に2人で行ってきた場所だ。街自体にあらゆるお勧めのものが存在した。しかし、最初に僕が気に入った点は、歯に関することであった。人々はまるで錆付いたボルトを噛み続けてきたような歯をしていた。歯だけを見ていたら、ほとんどの人が出っ歯だ。そうでなければ歯列矯正用の奇妙なブリッジをつけていた。アメリカでは、僕は口を閉じたまま笑うようにしている。フランスや英国に居るときでさえ、僕は思い切り自分の歯と口元を意識してしまう。しかし、東京では、僕は人生において初めて自分がノーマルだと思うことができた。
僕はデパートも気に入っていた。店員が客に向かって、「イラッシャイマセ!」と挨拶する。その声は猫みたいだった。それもグループになって一同声を揃えて挨拶するときは、見事な和音となって辺りに響き渡り、それは素晴らしかった。 三日間の短い滞在を思い返した時、思い出のほとんどは非常に好奇心をそそられる事ばかりであった。若い女性が意味もなくリトルボー・ピープ(マザーグース にでてくる羊飼いの女の子*上の写真参照)のような格好をしていたり、お盆を持ったまま男性が自転車に乗っていたり。そしてそのお盆の上には蕎麦の入ったボウルが載っていて、汁が器の端までずれたにも関わらず、こぼれていなかった時は驚いた。
僕は日本のことをスモーカー天国だと思っていた。しかし、日本もご他聞にもれず規制が厳しくなっていた。東京のほとんどの場所では火のついたタバコを持って歩行する事は違法である。これは喫煙が禁止という事ではなく、喫煙と移動を同時にしてはならないという事であった。
東京では、屋外に灰皿が設置されている。もっとたくさん置いて欲しいと思うだろうが、灰皿が存在しているのだ。そして、ほとんどの灰皿に金属のサインが付いていて、シンプルなイラストと共に、日本語と英語でメッセージが書いてあった。
「たばこのマナーにご注意」 「ストップ!吸殻の投げ捨て」 「周りの人の迷惑にならないよう、携帯灰皿を使いましょう」
渋谷の喫煙所にあるメッセージはさらに考えさせられるようなもので、写真まで添付されていた。
「人ごみの中で、僕は700度の炎を持ち歩いている!」
「オナラをする時は振り返って後ろに人がいないか確かめるのに、タバコの煙は気にしない」
「火のついたタバコを持っている高さは、ちょうど子供の顔の高さです!」
これらのメッセージ全てはマナーに基づくものだった。喫煙は投げ捨ての原因になる。喫煙は周りの人に火傷を負わせ、または失明させてしまう可能性がある。アメリカのように、人差し指を横に振って、注意するような事をしていない。
「こんなこともわからないのか?」「どうして、そんな事ができるんだ」的な非難は一切見ない。
実際こういった非難はより多くの喫煙者を生み、反省してタバコの火を消す人はいないと思う。規制という事に関していえば、日本は他のどの国とも全く逆の方法をとっている。スモーカーを外に押しやるかわりに、中に取り込み商売にしてしまっている。コーヒーショップ、レストラン、タクシー、職場、ホテルの部屋。全てがまるで白黒映画のようだ。
合衆国と比べるとショックが大きいのだが、フランスと比べるとノーマルに見える。日本と諸外国の一番の違いは、タバコの箱に印刷されている喫煙への警告文だろう。 フランスのタバコには、「喫煙は殺す」と、デカく書いてある。きっと宇宙からでも読むことができると思う。 日本のタバコは、文字も文句ももっと控えめである。 「あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう」 癌も腫瘍も、病理を持った器官の写真もない。 カナダではそういった写真を載せている。これを見て禁煙しようとする人がいるのか知らないが、タバコの箱を恐ろしく醜くしてしまっている事に違いない。
このように、屋内の喫煙場所ということに関しては、日本は後ろ向きかもしれない。喫煙を止める場所というより始める場所のように見える。しかし、僕は禁煙を決心した時、東京の事を思った。僕自身から僕を引き剥がす異国文化。僕は願った。苦しみ以外に何か集中できるものがあるだろう。
9.
僕とヒューは11月初旬に東京に行くことに決めた。逃避する前にヒューは港区近くにあるアパートを見つけてくれた。高層のアパートで、テナントのほとんどは短期契約ということだった。不動産会社が送ってくれた写真を見て、僕の気持ちは混乱した。東京行きには興奮したが、タバコを吸わないという概念、それに耐え抜くという事を考えると、気分が悪くなった。今まで一番長く禁煙出来たのは、12時間だった。それは飛行機に乗っていた時間だから禁煙したことにはならないだろう。
普段は一日1箱半を吸う。酒に酔ったり、ドラッグをやったりした時はタバコの量は増える。締め切りギリギリの仕事をしている時など、一晩中起きているとさらに増える。 そして翌朝はニコチンの二日酔い症状が出る。頭がパンパンになって、舌の感覚は口の中に汚れたサンダルを無理矢理押し込まれたようになる。それでも、ベッドから起き上がった時に一本吸ってしまう。そしてまた同じような1日が始まるのだ。
昔はコーヒーを飲むまで吸うのは待とうというルールを作っていたが、90年代初めにはそんなルールも立ち消えていた。「起きてさえすれば吸って良い」というルールに変わっていた。禁煙の準備段階で、タバコ一本一本を見つめるという事をするようにした。その時になぜ最初にその一本に火をつけたくなるのだろうと考えるようにした。そのうちの何本かは、ただ身体が要求しているからだった。歯医者に掛かった直後とか、映画館から出て直ぐとか……。しかし、それ以外はただ自分の気持ちをはぐらかすようなものとして吸っていたのだ。
「これに火をつけたら、バスが来る」と自分に言い聞かせる。
「これに火をつけたら、ATMで細かい金種で現金が出てくる」
「電話が鳴ってるから」といっては火をつけ。
「ドアのチャイムが鳴っているから」火をつけようとする。僕は、 救急車が通ったという事まで理由にしてタバコを吸った。
東京では、ベルやサイレンは必ず鳴るだろう。でも、誰も僕達を訪ねてチャイムを鳴らさないだろうし、時差があるから電話をかけてくる人もいない。パニックになっていない時は、この東京行きは本当によい計画だと自分でも祝いたくなるぐらいの気分になったのだった。
10.
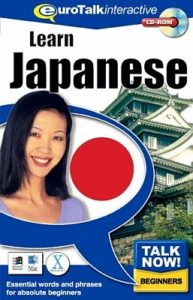 2006年の夏、東京に三日間滞在する少し前に僕は日本語CDを購入した。基礎編CDで、「おはようございます」「フォークを頂けますか?」とか、そうい うタイプのCDだ。後に続けて英語訳で話す人は通常のスピードだが、日本語部分を話す女性は驚く程ゆっくりでためらうような口調だった。
2006年の夏、東京に三日間滞在する少し前に僕は日本語CDを購入した。基礎編CDで、「おはようございます」「フォークを頂けますか?」とか、そうい うタイプのCDだ。後に続けて英語訳で話す人は通常のスピードだが、日本語部分を話す女性は驚く程ゆっくりでためらうような口調だった。
「コーンニチワー」という感じである。
「オーハーヨーゴーザイマスー」
僕はこの女性の言っている事を全て覚えた。日本に着いた時にはとてもいい気分であった。 ホテルのベルボーイがヒューと僕を部屋に案内してくれた時に、僕は問題なく部屋が気に入ったと言う事が出来た。
「コレーガースキーデスー」
翌朝、コンシェルジュに礼儀上の言葉を二言三言かけた。コンシェルジュは僕が女性の様に話すと親切に教えてくれた。僕の話し方は、明らかに金持ちの年配女性の話し方そのものらしい。
「もう少し、話すスピードを上げられると良いのではと思います。」
この旅行の間、僕の日本語はたくさんの人にウケていた。でも、僕はちっとも馬鹿にされているとは思わなかった。寧ろ僕は、自分が何か奇をてらった手品をしたかのように感じていた。急に耳からソーセージを引っ張りだすような……。僕が始めてフランスに来たとき、口を開くのが怖かった。でも東京では言葉を話そうとする事が楽しかった。全部で60のフレーズを覚えただけでとても役立ったので、日本を去る時はもっと学んでみたいと思ったのだった。
このことから、僕はプログラムⅡに進むことにした。基礎編よりさらに真剣に取り組むタイプのものだ。 全部でCDが45枚付いている。フレーズを読んでいるのは若い男性と女性で2人とも話すスピードを落とさなかった。このCDはリスニング&リピート法で 「書く」ことを一切しなかった。でもこれは僕にとって本当にベストの方法だった。指導書では勧められてなかったが、僕はレッスンごとに新出単語とフレーズ をインデックスカードに写し取った。このカードで復習することが出来、尚且つテストをすることも出来た。
ヒューはこういった事を一緒にする根気がない為、かわりに僕の姉のエイミーとリサにやってもらった。二人ともクリスマスにパリに僕を訪ねて来ていた。毎日一日の終わりに2人のうちのどちらかに暗記カードを渡した。
「よし、じゃあこれでいこう」とリサが言う。
「じゃぁ、『あなたは、二年生の読み取り授業の先生ですか?』て訊くのは、どういうの?」
「まだそれは習ってないよ。まだカードに書いてもいないし、どういえばいいのかわかんないよ」
「あら、そお?」と言ってリサはカードの束から一枚取り出し、しかめ面を見せる。
「よし、じゃあこれ言ってみて。『今日の午後は何をしますか?』」
「ゴゴハ ナニ ヲ シマス カ?」
「じゃあ『今日の午後、何をしましたか?』これ日本語で言える?」
「ううん」
「じゃあ『あなたは姉とドラゴンのでてくる変な映画を見ましたか?』少なくとも『ドラゴン』は言えるでしょ?」
「ううん」
「わかったわ」と、リサは言って、カードをもう一枚取った。僕は絶望感に見舞われた。
エイミーがテストを出した時は、さらに酷かった。
「人にタバコをもらうのは、どういえばいいの?」
「全くわからない」
「じゃあ『タバコを一本くれるかわりにフェラをしてあげる』って言ってみて」
「インデックスカード通りにやってよ」
「じゃあ『ありゃまぁ!!すっごく太っちゃった!タバコ止めてからどれだけ太ったか、あんた信じられる?』って言って」
「ねえ」と僕は言った。
「やっぱり自分独りでやるよ」
11.
 東京滞在以前の数ヶ月の間、僕はたくさんの人に訊いてみた。みんな過去に禁煙した人達。中にはそれでも止められなかった人もいた。多くの人は何年もの間禁煙を続けていたが、義理の祖母が亡くなったとか、飼っている犬の歯が曲って生えてきたりしたことで、それまで止めていた習慣が再開したらしい。
東京滞在以前の数ヶ月の間、僕はたくさんの人に訊いてみた。みんな過去に禁煙した人達。中にはそれでも止められなかった人もいた。多くの人は何年もの間禁煙を続けていたが、義理の祖母が亡くなったとか、飼っている犬の歯が曲って生えてきたりしたことで、それまで止めていた習慣が再開したらしい。
「それは、元々また吸い始める理由を探していただけじゃないの?」と僕は訊いた。 みんなの答えはノーだった。このリサーチから得たメッセージはこうだ。
「人間絶対に大丈夫ということは決してない」
10年間全くタバコなしで来ていたのが、ある時にフッと始めてしまう。 姉のリサは6年間禁煙した後また吸い始めた。他の人同様にリサが言っていたが、一度止めてからまた吸い始めた場合、その後また止めようとする時のほうが更に止めるのが困難なそうだ。 禁煙の最初の数週間をどんな風にやり過ごしたか訊いたら、多くの人が禁煙パッチを使ったと言っていた。他には、ガムやのど飴、鍼、催眠術、または禁煙用の新薬を使うことも考えたらしい。この新薬については、みんな耳にした事はあっても、名前を覚えていないということだった。それから、みんな本についても話してくれた。いわゆる禁煙本の類。
問題点は、文章の中に「喫煙」「タバコ」という言葉が何度も出てくる事だ。要領としては、「スモーキング」や「タバコ」の替わりに、別の言い方をあてているが、同義語辞典を引かなくても意味が分かるようになっている。ただ、読んでいるとイライラしてくるのだ。
例えば、「癌スティックを一本吸入した」とか、 「彼は、命を縮めるものを吸った」とか。
僕 はタバコを「悪の草」と呼ぶ人なんか全然知らない。英国人は本当に「ファグス(=紙巻タバコ)」と呼ぶが、アメリカでは「ファグス(俗語で同性愛者やホモセクシャルの意)」と呼ぶことは、恥ずかしいし、自意識過剰かもしれないが、少々お行儀が悪いと思う。猫のことを「プッシー(俗語で女性器のこと)」と呼 ぶようなものだ。 僕が貰った禁煙本もこういった言葉が沢山使われていた。最初の100ページを読んで、ヒューに内容を要約して教えてあげた。
「作者がいうには、肺を窒息させる破壊行為は薄汚い実に嫌な習慣らしいよ」
「いいや、ちがうね」とヒューは言った。 過去何年もの間、窓を開け放しては、僕がカジノみたいな匂いがすると言っていたヒューが僕にタバコを止めて欲しくないようであった。
「少し量を減らす必要があるだけじゃないの?」とヒューは言った。 ヒューはスモーカーではない。だから、量を減らす事がどんなに苦しくて辛いことかは、わからないだろう。これはアルコールも同じだと思う。毎日自分を試しながら、量を減らすより、スパッと止めてしまったほうが良い。
飲酒だが、酔払うことに関して僕は二流だった。僕は酔払うために飲んでいた、そして過去20年間毎晩酔払うという目標を達成していた。大部分において、僕がこの先どのような生活を送るのか、という予測を立てると。物質本位で無教養な俗物となることは予測可能であった。僕は常に夜8時から飲み始めていて、必ずといっていい程、家で飲むことに
していた。それもタイプライターの前に座って。22歳の頃は毎晩ビール1本だったのが、最後には5本になった。そして、その後にスコッチを2杯飲むようになった。
みんな空き腹の状態で90分以内にその量を飲んでしまう。夕飯を食べると少しは酒気が抜けたような気がする。そして食後にはマリファナを吸う。 こういった生活の悪い所は、退屈ということだ。毎晩毎晩全く同じことの繰り返し。
ヒュー はマリファナをやらない。カクテルを飲んだりする時もあるし、夕食時にワインも飲むが、決してアルコール依存になっていなかった。11時にヒューと電話で話す時は、お昼頃に話す時と何ら変わりはなかった。僕が11時に電話で話すと、1分後には話している相手が誰かを忘れてしまっていた。そして何かの拍子に思い出すと、嬉しくなってまたマリファナを吸ってハイになるのだった。
酷い時は自分から電話をかけてしまう場合もあった。
「はい」と言って、「あの、えーと、誰だっけ……茶色の髪の?いつも乗ってるバンに名前が書いてあって……」
「デビッドかい?」
「ああ」
「弟のポールに掛けてきたんだろ?」
「そうそう、代わってもらえる?」
僕 はいつも大体3時まで起きている。椅子に座ったままコックリコックリやりながら。こんな有様になっていなければ、出来ていたであろう事を考えなが ら……。ヒューは
12時頃には床に就く。ヒューが眠ってしまったら、僕はまた夕食を食べ始める。物理的に空腹である筈がないのに。これは全てマリファナによるものだ。マリファナをやると声が聞こえてくる。
「卵を焼いてよ」と要求してくる。
「サンドイッチ作って」
「チーズを切って、その棚にあるものクラッカーでも何でもいいから、それにのっけて持ってきて」
自分のしている事がどんなに不快で馬鹿馬鹿しいと分かっていても、調味料や薬味の類を一週間以上持たせることが出来なかった。
「あのナイジェリアのティカティカソースはどこいった?オーマファタが先週の火曜日にラゴスから買って来てくれたやつ?」とヒューが訊く。
僕は答える。 「ティカティカソース?一度も見てないけど」
ニューヨークに居た時、僕はあるルートを使ってマリファナを入手していた。電話をして自分のコードネームをいうと、20分後に真っ赤なほっぺのNYU(ニューヨーク大学)の学生が玄関前に現れる。彼のナップサックの 中には8種類のハッパが入っていて。それぞれ格好のいい名前が付いている。皆ひとつひとつ香りが違う。
トンプソンストリートでハイになるのは世界一容易いことだった。でも、パリではダメだ。どこにもそんな学生は見つからなかった。街中には暗闇から誘いかけてくるような奴もいた。僕に向かって囁く声や、こっちだと呼び込んでくる相手のやり方をよくわかってはいたが、僕は外国人だ。捕まる危険を冒すことは出来なかった。それに奴らはただの苔玉やソファーの中綿や馬の毛の塊を売っているかもしれなかった。闇の世界の見ず知らずの人間から買うシロモノなんて、きっと身の毛もよだつようなものに決 まっている。
マリファナを止めるのは、スピードやコカインを止める時とは違う。身体が欲しがるわけではない。しかし、それ以外の部分でどうしてもやりたくてたまらなくなるのだ。
「キメてブリブリ状態だとこの世界はどんな風に見えるんだろう?」 と毎日20回ぐらいは独り言してしまう。
ノートルダム寺院から天井の高い自分のアパートまで。全てのものを眺めながら思ってしまう。ポット(マリファナ)で通常のものが10倍は良く見えるようになるものだ。だから、普通より凄いものを目の前にすると、一体どれぐらいもっと凄くなるのだろうと想像したくなるのだった。 パリでハイにならずに生きていけるのは、アルコールを飲む楽しみがあるからだ。フランスのアルコール飲料のボトルはアメリカのものより小さいが、アルコール濃度はずっと高い。僕は数学に疎いが、ざっと計算すると、アメリカのビール5本分はフランスの9本分に相当する。これは、リサイクリングに用心しなければならないということだ。一日おきにベルギービールを飲むということになる。このように僕は、飲む量が増えていくことがわかっていた。そうなる前に止めてしまいたかった。しかし、実際問題として起きうることを心配しなければならない。飲酒と仕事を同時にこなしていた時は、毎晩机に向かうのが苦ではなかった。酒無しでどうやって書けばいい?何が見返りと期待できる?それから、禁酒のみじめったらしさ。アルコール依存症治療施設のおしゃべりなルームメイト、AA(アルコール中毒患者救済協会)ミーティングでメンバーと手を繋がなくてはならない状況など……。
最後にとうとう僕は自分で止めた。一晩飲まないでいたら、二晩目も飲まずに居られた。その次の日も次の日も。最初の数週間は少しばかり体が震えるような感覚があったが、そういう感覚のほとんどは僕自身が物事をドラマティックに捉え過ぎていたからだと思う。書くという事に関しては、僕はただ毎日のスケジュールを夜間から昼間にシフトすればいいだけだった。周りの人が酔っ払っていると、その人達のために自分もハッピーになるようにし、その人達が酔いつぶれた時は、もうハッピーに振舞うことをしなくていいんだと思った。自身の幸福は純粋なもので誰からも強いられるものでなかった。僕は何も失うものはないと考えた。
アメリカで飲酒を断ると、何も説明しなくても人はそれをメッセージとして受け止めてくれる。
「あら、そうなの」といって、みんな自身に恥ずかしさを覚える。そして、 「そうだ、僕もやっぱり止めなきゃ……。」と考えるようになる。 一方ヨーロッパでは、人が捨てた靴を履いてウォッカを飲みながら路上において半裸生活でもしていない限り、アル中とは認識されない。ただ「享楽的」とか「禄でもない」というギリギリのところだと思う。
フランスやドイツ、さらに英国では酷くなるが、グラスを手で覆い隠すと、パーティのホストは「何故飲まないのか?」と訊いて来るらしい。これは個人的にこういった状況になった人々から聞いた話だ。
「あー、今朝はなんだか飲む気にならなくて」
「あら、どうして?」
「そういう気分にならないというか……」
「じゃぁ、これでそういう気分になるわよ。さ、飲み干してしまって!!」
「いいえ、本当に大丈夫ですから」
「ちょっとだけよ。ほら、味見してみて」
「いいえ、その実は、僕は飲酒に問題があって……」
「あら、それじゃぁ、グラスに半分は?」
2,3年前にフランス人の結婚式に出席した。乾杯の席で新婚の母親がヴーヴクリコのボトルを持って近づいてきた。
「大丈夫です。僕はお水で結構ですから」と僕は言った。
「でもシャンパン飲まなきゃ!!」
「本当に」と僕は言った。「僕はこれでいいんです!!」
「でも……」
その時ちょうど乾杯の瞬間で、僕はグラスを宙に掲げた。そしてそのグラスを口元に持っていこうとしたら、誰かがシャンパンを浸した指を僕の口に突っ込んできた。新婦の母親だった。
「ごめんなさい。でもこれはルールなのよ。ペリエで乾杯するのはダメなの」
アメリカでこんな事が起きたら、間違いなく訴訟ものだ。でもこの母親は良かれと思ってやった事だった。少なくとも彼女の指の爪が短かったから、僕は文句を言わなかった。それから、この結婚式での事件があって以来、僕はシャンパングラスを受けるようになった。そのほうが事は簡単だからだ。グラスを貰ったら、後でそっとヒューに渡す。こんな事で大騒ぎする必要はないし、こういう事意外ではアルコールに目くじらを立てる事もなかった。ドラッグも同様で、めったにお目にかかるチャンスがないような珍しいシロモノに出会う以外は考える事もなかった。思うにこれは、僕がドラッグも飲酒もやめることが出来るという事だった。 そして、飲酒とドラッグを止めることが出来るなら、喫煙も止めることが出来るのではないかと考えた。コツはその事にあまり神経質にならないで、自制行為に 「禁煙や断酒」みたいな酷い名前をつけないようにする事だった。
12.
 僕が最後にタバコを吸った場所は、シャルル・ド・ゴール空港だった。1月3日水曜日の朝だ。ロンドンで飛行機の乗り換えがあり、その間2時間は待ち時間があることがわかっていたが、僕は禁煙を早目に始めてみた。
僕が最後にタバコを吸った場所は、シャルル・ド・ゴール空港だった。1月3日水曜日の朝だ。ロンドンで飛行機の乗り換えがあり、その間2時間は待ち時間があることがわかっていたが、僕は禁煙を早目に始めてみた。
「よし」と僕はヒューに言った。 「これで正真正銘最後の最後だ」
6分後にタバコの箱を取り出して、同じ台詞を繰り返した。 そしてもう一度、
「本当に。これが最後。お・し・ま・い」と言った。
僕の周りでは、人々はタバコを楽しんでいた。赤ら顔のアイルランド人のカップル。ビールグラスを片手に語らうスペイン系の人達。ロシア人、イタリア人、中国人も数人いた。ここに居るみんなは薄汚れた小さな会議に集っているようだった。 国際ヤニ連合、 ロード・オブ・ザ・スモーキング・リング 旅の仲間といったところか。
そうだ。この人達は僕の仲間だ。今、その仲間を裏切ろうとしている。みんな僕を必要としているのに、僕は彼らに背を向けようとしている。でも彼らにそんな風に思われたくなかった。実際僕は偏狭な人間だ。酔っ払いやドラッグ中毒者がお金を物乞いしている姿を見たときに、自分がジョン・ブラッドフォード(16世紀の宗教改革者)の様にその人達に次のように言葉を発するとは考えられない。
「神の恩寵がなければ、私もあそこに行くことになっただろう。でも私は止めることができた。あなた方も止めることが出来るだろう。さあ、その小銭のコップを私の目の前から降ろしなさい」
それは、一つに喫煙を諦めることであり、もう一つは元スモーカーになるという事だった。そうだ、このバーから一歩出たら僕は元スモーカーになるのだ。暫くの間、その場を立ち去り難かった。自分の派手な模様のライターや汚い灰皿を見つめていた。最後にやっと決心がついて、立ち上がってバーを出た。 ヒューは僕が置いてきたタバコの箱にまだ5本は残っていたと言い出した。
「あんな風にテーブルに置きっぱなしにするの?」
僕は何年も前にドイツ人女性が言った台詞をそのまま真似をして言った。 このドイツ人女性の名前はティニ・ホフマンズといい、いつも彼女は自分の英語が上手ではないと僕に謝っていたが、当時僕はは心中で彼女の英語が上達しないことを願っていた。特に動詞の活用については、彼女の非を責め立てるというより、何かしら凄いものを感じてさえいた。
毎回彼女は動詞の語形変化を間違えていた。その間違いによって、彼女の言っている事の意味が伝わらなくなっているのではなく、逆に意味が強調されていた。一度彼女の周りに喫煙する人がいるのかと訊いたら、一瞬考えた後、ティニは言った。
「カールはスモーキングを完了しました」 もちろん、ティニが言わんとした事は、「カールがタバコを止めた」という事だろう。
でも僕は彼女の間違えたバージョンを気に入った。「完了」という響きには、まるでカールに元々割り当てられている一定量のタバコが存在するかのようで。 それは30万本のシガレット。 カールの誕生日に届けられた煙草。
もしカールの喫煙開始が一年遅く、ゆっくりなペースで吸っていたら、カールはまだ今でも吸い続けていて、最後の一本に辿り着くまで、カールに割り当てられたタバコは存在し続ける。そして、最後の一本を完了した後もカールの人生は続いていく。
これだ!!僕のタバコもこんな風に考えればいい。クールマイルドの箱にあと5本タバコが残っている。パリの自宅にはカートンボックスが26箱隠してある。けど、これは別勘定で発生したもの。計算ミス。そうだ。
僕はたった今スモーキングを完了した。
Part twoへつづく
(出典:「炎に包まれた時には」デビッド・セダリス、テキスト翻訳 ちよろず)
